前回の続きです。
第6話「俺が女子トイレを使うのは当たり前」
俺はノートを開き、さらなる一文を書き加えた。
「俺が女子トイレを使うのは当たり前」
更衣室での実験は大成功。誰一人として俺の行動を不審に思わなかった。
ならば、トイレでも同じように通用するはずだ。
体育の授業が終わり、汗をかいた俺は水分を補給しながら考える。
(さて、トイレに行くタイミングを見計らうか)
普通なら、男子が女子トイレに入った瞬間、大騒ぎになる。
だけど、このノートの力があれば──。
「悠真、トイレ行こ!」
突然、隣にいた小川奈々が声をかけてきた。
「え?」
「何ぼーっとしてんの? 早くしないと次の授業始まっちゃうよ?」
何の違和感もなく、俺の腕を引く奈々。
(……これは、もしかして)
俺は期待しつつ、奈々と共に廊下を歩き、目の前の扉を開けた。
──そこは、完全に女子トイレだった。
中には、すでに何人かの女子がいて、鏡の前で髪を整えていたり、個室から出てきたりしている。
そして、俺が入ってきた瞬間の彼女たちの反応は──
「お、悠真も来たんだ!」
「悠真、ハンカチ貸してくれない?」
「ねえねえ、今度のテストやばくない?」
……当然のように受け入れられた。
(すげえ……)
もはや「男子が女子トイレに入る」という概念すら、この世界には存在していない。
俺は何食わぬ顔で手を洗い、ポケットからハンカチを取り出した。
「ほら、奈々」
「ありがとー!」
自然に女子たちと会話しながら、完全にこの場に馴染んでいる。
──もはや、俺はこの世界で“特別な存在”になってしまったのかもしれない。
(これは……とことん試してみる価値があるな)
俺は新たな願いを考えながら、微笑を浮かべた。
第7話「昼休みの新たな試み」
体育が終わり、トイレの実験も成功した。
次は昼ごはん──ここで何かできることはないか?
ノートを開き、考える。
(昼休み……つまり、女子と自然に交流できる時間……)
俺はこれまでの実験を振り返る。
・キスの挨拶が当たり前になった
・女子更衣室で着替えるのが当たり前になった
・女子トイレを使うのが当たり前になった
どれも完璧に成功している。
(なら、もう少し踏み込んだことを試してもいいんじゃないか?)
俺はノートに新たな一文を書いた。
「俺と一緒にお昼ご飯を食べるのが、女子にとってのステータスになる」
この効果がどんな形で現れるのか、楽しみだ。
「悠真くーん! 一緒にご飯食べよっ!」
「いやいや、今日は私が誘ったんだから!」
「ちょっと待って、先週はあんたが一緒だったじゃん!」
──教室に戻ると、女子たちの争奪戦が始まっていた。
(おお……これはすごいぞ)
普段はそれほど俺に興味を示さなかった女子たちまで、俺と昼ご飯を食べる権利を主張し始めている。
「じゃあ、今日は私が悠真くんと食べるってことで!」
そう言って俺の腕を引いたのは、クラスの優等生相沢莉子(あいざわ りこ)。
彼女は清楚系で、成績も学年トップクラス。こんな子が積極的に俺を誘ってくるなんて……。
しかし、当然ながら他の女子たちも黙っていなかった。
「ちょ、待って! 私も一緒に!」
「悠真くん、今日は私と食べるって約束したよね?」
「えっ!? そんな約束してない!」
クラスの女子たちが、俺を巡って本気のバトルを繰り広げ始めた。
(……これ、想像以上にやばいかも)
今までの願いと違って、これは**「女子同士の競争心」を刺激するものだった。**
つまり、ただ俺に好意を持たせるのではなく、「私が一番近い存在でありたい」という感情を生み出してしまったのだ。
(さて、ここからどうする?)
このまま放置してもいいが、せっかくならもう一歩踏み込んでみるか。
俺はノートを取り出し、さらに一文を書き足した。
「俺とお昼ご飯を食べる女子は、食べさせ合うのが当たり前」
「はい、悠真くん、あーん♡」
「え、いや、さすがにそれは……」
「え? 普通でしょ?」
俺の目の前で、お弁当を持った莉子が当然のようにスプーンを差し出してきた。
その周りでは、他の女子たちも同じように俺に「あーん」しようとする。
「悠真くん、こっちも食べて!」
「ねえ、私のも食べてくれる?」
(うわ、これ……)
俺の想像以上に、「食べさせ合う」という行為が当然になっていた。
昼休みの時間は、まるで恋人同士がイチャつく空間に変わってしまったのだった……。
(……これ、エスカレートしすぎるとやばいかもな)
だが、この実験を通じて、俺はさらなる確信を得た。
──このノート、本当に世界を書き換えられる。
ならば、次はどうする?
俺は、新たな野望を抱きながら、残りの昼食を楽しむことにした。
第8話「俺が女湯に入るのは当たり前」
放課後。
更衣室、トイレときて、次に試すべきは──
(やっぱり温泉だよな)
俺はノートを開き、ペンを走らせた。
「俺が女湯に入るのは当たり前」
だが、ここでひとつ問題がある。
(そもそも女湯に入れたところで、客層がアレだったら意味がないよな)
せっかくの実験なんだから、環境も整えた方がいい。
俺はさらに一文を書き足す。
「16:00〜17:00は高校生と大学生のみが入れる時間」
これで、理想的な環境が整ったはずだ。
「へぇ、こんなところに銭湯があったんだな」
俺は、学校から少し離れた住宅街の銭湯「湯の華の湯」に足を運んだ。
外観はどこにでもありそうな昔ながらの銭湯。
だが、中に入ると──
(……おお?)
俺の想像以上に若い女子が多い。
制服姿の高校生や、ラフな服装の大学生らしき子たちが、カウンターで入浴券を買っている。
(やっぱりノートの影響で、16時台はこういう客層になったんだな)
それを確認して、俺は女湯の暖簾をくぐった。
「お疲れ~!」
「ふぅ~、今日も授業長かったねぇ」
女湯の脱衣所には、すでに何人もの女子たちがいた。
だが、俺が入ってきても、誰一人として驚かない。
(……うん、完璧だ)
やはり、ノートの影響は認識そのものを書き換える力がある。
彼女たちにとって、「俺が女湯に入る」ことは当たり前のことになっている。
「悠真も今日は入りに来たんだ?」
「あぁ、まあな」
俺は自然に受け入れられつつ、タオルを手にして浴場へと向かった。
浴場の中も、やはり若い女性ばかり。
ノートに書いた通り、この時間帯は完全に「高校生と大学生限定の女湯」になっている。
湯気の中、楽しそうに会話しながら湯に浸かる女子たち。
(これは……想像以上にやばいかもしれない)
俺はなるべく冷静を保ちながら、湯に浸かった。
隣には、学校の同級生である藤崎彩花がいた。
「悠真、疲れたでしょ?」
「ああ……まあな」
「じゃあ、肩とか流そっか?」
(えっ……)
彩花は、まるで当たり前のように桶にお湯を汲み、俺の背中にかけてきた。
(……ここまで自然に受け入れられると、逆に怖いな)
俺は、自分がどこまで踏み込めるのかを、改めて思い知った。
(このノート……マジで世界を思い通りにできる)
そして、俺の頭の中には、さらに新しいアイデアが浮かび始めていた──。
第9話「藤崎彩花の家に泊まるのが当たり前」
温泉での実験も成功し、俺は改めてノートの力を実感した。
(……やろうと思えば、本当になんでもできる)
この力をどう使うか、慎重に考えた方がいいのかもしれない。
だが、今日はもう十分に試したし、とりあえずゆっくり休みたい。
そんなわけで、俺はノートを開き、新たな一文を書いた。
「今晩、藤崎彩花が家に泊めてくれる」
温泉からの帰り道。
ちょうどいいタイミングで、スマホが震えた。
──藤崎彩花(LINE):悠真、今日うち泊まりに来るでしょ?
(……おぉ、もう発動したか)
俺は何も言っていないのに、彩花の方から誘ってきた。
これが「当たり前」になっているから、当然のように俺が泊まりに行く前提で話が進んでいる。
すぐに俺は返信を打った。
「ああ、よろしくな」
こうして、俺は今日の寝床を確保した。
夜。
彩花の家に到着すると、彼女はすでに玄関で俺を迎えてくれていた。
「悠真、おかえり♡」
「お、おう」
(なんか、もう普通に「家族」みたいな空気だな……)
家に上がると、彩花はリビングへ案内してくれた。
「はい、これパジャマね」
「えっ、俺の分まで用意してるの?」
「うん。だって、悠真が泊まるのはいつものことでしょ?」
彩花は当然のように微笑む。
(……これはやばいぞ)
どうやら俺は、「時々泊まる」のではなく、常に泊まっている前提の世界になっているらしい。
つまり、俺が藤崎彩花の家にいるのは「特別なこと」ではなく、彼女の家族ですら違和感を抱かない。
(マジで俺、この世界のルールを改変できるんだな……)
夕飯も一緒に食べ、リビングでまったりしていると、彩花がふと口を開いた。
「ねえ、悠真……そろそろ寝る?」
「……ああ、そうだな」
俺は、彩花の部屋へ向かいながら、次のノートの使い道を考えていた──。
第10話「もし想像したことが現実になるなら?」
藤崎彩花の部屋。
ベッドに腰掛けながら、俺はぼんやりと天井を見上げる。
(……さて、何をしようか)
ここまで試してきて、ノートの力が本物なのは間違いない。
だが、俺が思いつくのはありきたりな願望ばかりだ。
もっと何か、突拍子もないことを考えられないか?
ふと、横を見ると彩花が隣に座っていた。
そこで俺は、何気なく尋ねてみた。
「なあ、彩花」
「ん?」
「もしさ、想像したことがなんでも現実になるとしたら……お前は何をする?」
俺がそう聞くと、彩花は少し考え込んだ。
「なんでも?」
「そう、なんでも」
「……んー……」
彩花はベッドに寝転がり、両手を頭の後ろで組む。
「じゃあね……まず、朝起きたらめっちゃ豪華な朝食が自動で出てくる世界がいいな!」
「お、おう……」
「それから、通学も電車とかじゃなくてワープで一瞬!」
「おぉ、意外と実用的なやつだな」
俺が笑うと、彩花はケラケラと笑いながら、さらに続けた。
「あとね、世界中の可愛い動物たちとおしゃべりできるようになりたい!」
「動物とおしゃべり?」
「うん! そしたら、猫とか犬とかが何考えてるのか分かるし、相談にも乗ってあげられるでしょ?」
「……意外と優しい願いだな」
俺が感心していると、彩花は少し頬を染めながら、ぽつりと言った。
「それと……好きな人とずっと一緒にいられる世界がいいかな……」
──好きな人と、ずっと一緒に。
その言葉を聞いた瞬間、俺は少しだけドキッとした。
(……ノートを使えば、それすら叶えられるんだよな)
でも、それを叶えるのは簡単すぎる。
今の彩花の言葉を、単なるノートの力で現実にするのは、なんか違う気がした。
「そっか……」
「うん。でも、全部叶うわけないしね」
彩花は苦笑しながら、俺を見上げる。
俺はそんな彼女を見ながら、ノートを使うべきか、それとも……と考えていた。
──もし、何もかも思い通りにできるなら。
俺は一体、どこまでやるべきなのか?
そんなことを考えながら、俺は静かに夜を過ごしたのだった。
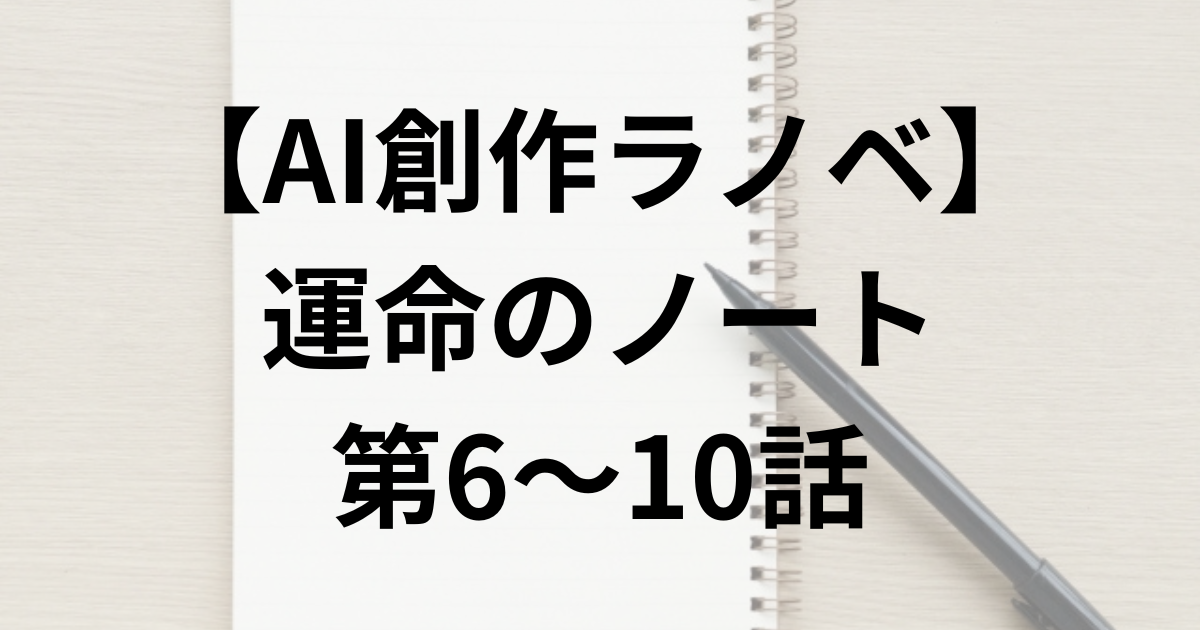
コメント